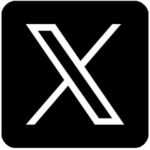たしか中学校の国語の教科書に「一切れのパン」という話が載っていた。
第二次世界大戦中、ハンガリーの首都ブダペストで主人公は二十歳くらいのルーマニア人男性。彼には妻がいて、ドナウ川を往来する船で働いている。国際情勢が変化しての話。当時ハンガリーはドイツについていたが、彼の祖国ルーマニアは反ドイツのソ連についたため、彼は敵国人として捕らわれ、運搬列車に押し込まれてしまう。その貨車の中でユダヤ人の老人ラビと出会う。しかしルーマニア人として捕らわれている。主人公と数人の捕虜たちは、列車の床板を外して脱走することになった。ラビは主人公に自分も一緒に行きたいと言ったが、主人公はやめたほうがいいと忠告した。ラビはユダヤ人なので脱走して捕まったら酷いことになる。このままルーマニア人捕虜としている方がいいと説得した。ラビはその意見を聞き入れ、主人公にハンカチの包みを手渡した。「この中には一切れのパンが入っている。但し、すぐ食べてはいけない。パン一切れ持っていると思うと我慢強くなれる」とラビは言った。包みを受け取った主人公はラビを残して貨車から脱走。その間、主人公は何度も空腹に襲われたが、ラビの忠告を守ってハンカチの包みを開けることはなかった。それが実って、主人公は無事に妻が待つ我が家に辿り着いた。そしてその時、包みを開けると、中から出て来た物はパンではなく木片だった。
当時とても印象深く残っているが、こういう仕事をしていると、困ったときのよりどころと重なる。身体の問題にしても心の問題にしても会社の問題にしても困ったときに頼れるところがあることがどれだけ有り難いことか。昔は私自身、師匠がいなかったから、難しい患者には本当に悩んだ。今は師匠がいるので難しければ先生に診てもらおうで終わりである。患者さんの悩みもこの症状はどこへ行ったらいいかわからないのが悩みとなっている。うちに来ていただければ、「これはすぐに病院に行ってレントゲン。」とか、「少し鍼だけで様子を診れば良い。」とか指導している。心のよりどころの有り難さは年を取れば取るほど身にしみる。