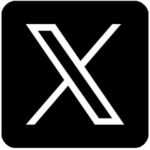以前、読んだ本の中に戦争時代の捕虜の話があった。
捕まった捕虜は目隠しをされて、腕に注射針を刺されこう言われる。
「今刺した注射針で少しずつあなたの血液を抜いていく。音が聞こえるだろう。やがてあなたは死を迎える。」
そして段々音が聞こえる。
「ポタン、ポタン、ポタン・・・・・。」
そうすると殆どの捕虜は恐怖のあまり死んでしまうと言う。
しかし実際は注射針は刺しただけで、一切出血させていないという。
これと同じような話を先日学会で聞いた。
「食道がんの患者が肝臓に転移をして、末期がんで余命6ヶ月と言われた。すっかり希望をなくし亡くなられた後、解剖したら食道がんは治っていて肝臓は良性腫瘍だった。人は意識で死ねるんです。」
この話も捕虜の話と同じである。
逆を返せば末期がんがあっても、意識で生きられると言うことである。
それぐらい人は意識が大事だという話である。
以前、学校で「一切れのパン」の話を習った。
時代は、第二次世界大戦中。場所は、ハンガリーの首都ブダペスト。主人公は二十歳くらいのルーマニア人男性。彼には妻がいる。ドナウ川を往来する船で働いている。
そして、国際情勢が変化した所から物語が始まる。当時ハンガリーはドイツについていたが、彼の祖国ルーマニアは反ドイツのソ連についたため、彼は敵国人として捕らわれ、運搬列車に押し込まれてしまう。
その貨車の中で老人ラビと出会う。ラビはユダヤ人であるが、ルーマニア人として捕らわれている。主人公と数人の捕虜たちは、列車の床板を外して脱走することになった。
ラビは主人公に自分も一緒に行きたいと言ったが、主人公はやめたほうがいいと忠告した。ラビはユダヤ人なので脱走して捕まったら酷いことになる。このままルーマニア人捕虜としている方がいいと説得した。
ラビはその意見を聞き入れた。そして、主人公にハンカチの包みを手渡した。「この中には一切れのパンが入っている。但し、すぐ食べてはいけない。
パン一切れ持っていると思うと我慢強くなれる」とラビは言った。包みを受け取った主人公はラビを残して貨車から脱走した。脱走した数人はバラバラになった方がいいと考えて、それぞれ別々の道を進んだ。
その後、主人公は兵隊や警官の姿を恐れながら、独りで数日さまようことになる。その間、主人公は何度も空腹に襲われたが、ラビの忠告を守ってハンカチの包みを開けることはなかった。
それが実って、主人公は無事に妻が待つ我が家に辿り着いた。そしてその時、包みを開けると、中から出て来た物はパンではなく木片だった。
人は「希望」で生きられる。